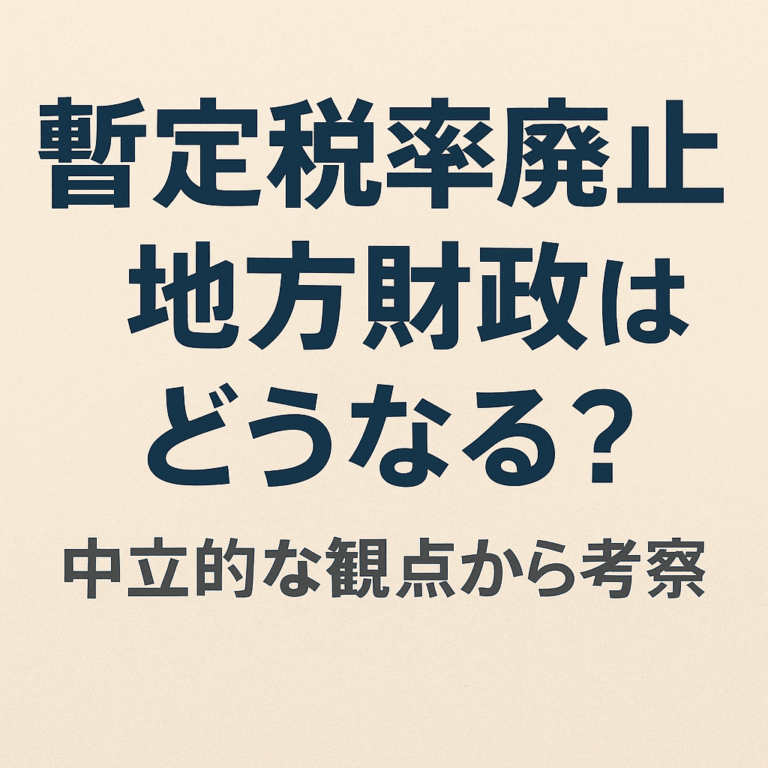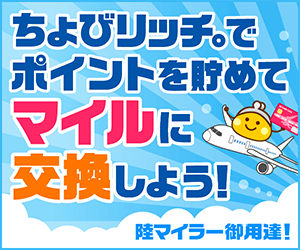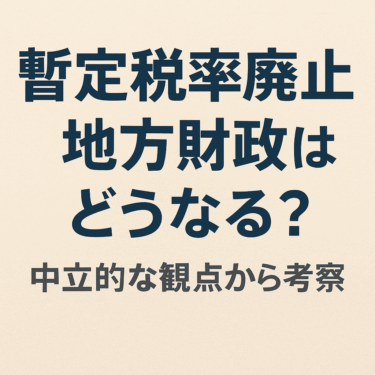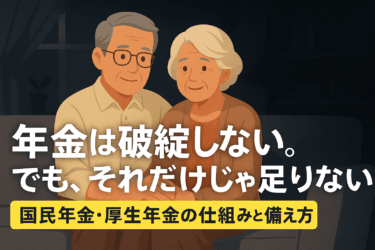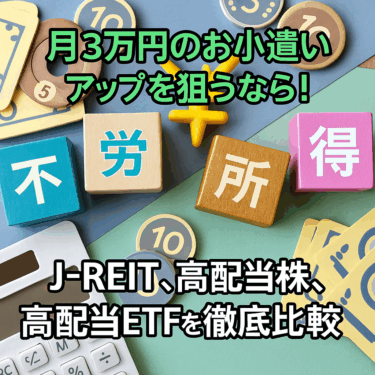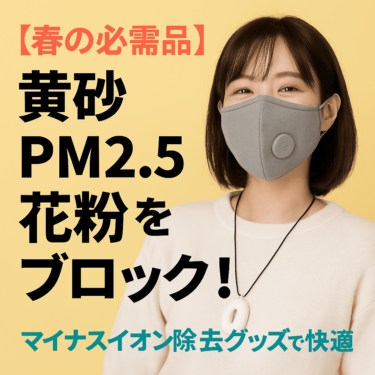1. はじめに
2025年、暫定税率の消滅論が再び潰上しました。 これに伴い、「地方自治体減収」というキーワードがマスコミの間で大きく騒ぎを呼んでいます。
では、この論争を中立視点で分析した場合、本当の課題は何なのでしょうか。
2. 暫定税率とは
暫定税率とは、ガソリン税や地方道路譲与税などにおいて、原本の法定税率に加税する形で設けられた「一時的」な税率を指します。 しかし、この暫定は50年以上続いており、そもそもの性質からして、消滅を言い出すこと自体は自然な活動です。
3. 国と地方の影響
暫定税率消滅で最も影響を受けるのは地方自治体です。
しかし、ここで見落としがあります。
- 税は国が軸維し、地方に分配している
- 地方は自主財源の5割以上を国に依存
そのため、税収が減ることによるダメージは大きくても、「こんなに依存していたのか」を明らかにしただけとも言えます。
4. マスコミはなぜ減税を嫌うのか
マスコミの報道も省みる必要があります。
- 財政破綻ストーリーを作りやすい
- 弱者の味方ポジションを保ちたい
- 宣伝済等の給付充実に配慮したい
これらが縁となり、減税を嫌う傾向が生じていると考えられます。
5. 本当に地方は困るのか
地方自治体にとっては直撃となる部分もあるでしょう。
しかし、それを機会として
- 減税による経済活性化
- 地方の自立性鼓促
- 地方税收改革の推進 などを進めるチャンスにもなりえるはずです。
6. 減税による経済効果の可能性
ガソリン価格下降による経済効果は大きい。 運輸業のコスト減少は物流業全体に映響し、消費物価の折り込みを低減させます。 さらに、可出分所得の増加は家計の余裕を生み出し、内震制御力を強める効果も期待できます。
実際には、運輸業総合経費が1%減ると、GDPを整體でも数千億円協で担う効果が期待されるとされます。
7. 地方自治体の創意工夫と自立促進
例えば、京都市は宿泊税を設け、観光徴情を税源として活用しています。 これは地域経済を支えると同時に、地方自立性を高める優れた例です。 さらに、倉敷市なども観光地として議論を始めており、次世代の税源創造に向けた動きが始まっています。
8. 各地方自治体の現実:名古屋市の例
名古屋市では、暫定税率消滅による減収は約300億円と評価されていますが、同市の総体予算は約3兆円。 割合で見ればわずか1%前後の減少にすぎず、これによって大きな行政止止を悪魔するのは遠近と言えるでしょう。 これを機会として、自主的な税收拡大策を推進する発想は欲しい所です。
9. 結論
減税は「7割置き」で語られるべきではありません。
減税にもリスクもチャンスもある。 しかし、実際に問われるのは、その後の設計と地方自立性をどう高めるかです。
これからTRCPとしても、感情論ではない、理性に根ざした記事を掲載し続けます。「当たり前のことを当たり前に言える」そんなメディアを相乗して。